このブログは「人類の目的」について考察する。今回は「そもそも目的とは何か」という観点で考察する。
目的という概念は直感的に理解されるが、厳密に定義しようとすると多層的な構造を持つことが分かる。この定義をはっきりさせた上で、目的の本質を整理するとともに、人類の目的を考察するベースとする。
1. 目的の基本構造
目的には、主観的・客観的・内在的・外在的の4つの層がある。
主観的目的
意識を持つ主体が意図的に設定する目的である。例えば、「幸福を追求する」「知識を深める」といった目標は、主体の意思によって決められる。
客観的目的
主体の意思とは無関係に、外部から見出される目的である。例えば、「生物の目的は生存と繁殖」「宇宙の目的はエネルギー拡散」といった考えは、人間が意識的に設定したものではなく、外部の観察によって認識されるものである。
内在的目的
主体の意識とは無関係に、システムや構造の仕組みとして存在する目的である。例えば、「DNAが自己複製を行う」「文明が発展を続ける」といった現象は、それ自体に意図があるわけではないが、結果として目的のように機能する。
外在的目的
他者や環境によって与えられる目的である。例えば、「神が生きる目的を与える」「社会が役割を決める」といった考えは、主体の意思とは別に、外部から目的が設定されることを意味する。
目的は、意識的に決めるもの(主観的目的)だけではなく、システムの性質や環境によって決まるもの(内在的・外在的目的)も含まれる。また、場合によっては、目的のように見えるが意識的に設定されたわけではないもの(客観的目的)も存在する。
2. 目的と関連概念の整理
目的を正しく理解するには、似た概念との違いを明確にする必要がある。
目的と目標の違い
目的は「最終的な方向性」であり、目標は「その目的を達成するための具体的な手段」である。例えば、「宇宙進出」が目的だとすれば、「火星移住」はその目標となる。目的は抽象的で長期的な指向性を持つが、目標はより具体的で達成可能な段階的ステップを指す。
目的と価値の関係
目的を設定するためには、それが「価値あるもの」と認識される必要がある。例えば、「幸福の追求」が目的になりうるのは、「幸福が価値あるもの」とされているからである。価値が変われば、目的も変わる可能性があるため、目的は価値判断と密接に結びついている。
目的と因果律の関係
目的は未来志向の概念であり、「こうありたい」という方向性を示す。一方、因果律は過去の結果を説明するものであり、「こうなった」という流れに従う。目的は因果の流れの中で設定されるものなのか、それとも因果の枠組みを超えた概念なのか、という点が重要な議論となる。
目的の固定性と可変性
目的が固定的である場合、どんな状況でも普遍的に存在するものと考えられる。例えば、「知識の探求は人類にとって普遍的な目的である」とする立場がこれに当たる。一方、目的が可変的である場合、環境や時代によって変化するものと考えられる。例えば、農耕社会では「生存と繁栄」が目的だったが、現代社会では「持続可能な発展」が重視されるようになっている。
3. 目的の成立条件
目的が成立するためには、以下の3つの条件が必要と考えられる。
第一に、主体の存在が必要である。
目的を持つためには、それを設定する主体が存在しなければならない。もし主体が存在しない場合、目的は外部から与えられるものになるか、単なる結果として解釈されることになる。例えば、人類が主体であれば、人類は自ら目的を設定できる。しかし、もし人類が主体ではなく、宇宙や神が主体であるならば、人類の目的は外部によって決定されるものとなる。
第二に、意図性・指向性が必要である。
目的は単なる結果ではなく、未来を想定し、意図的に設定されるものである。例えば、「科学技術を発展させる」という目的は、意識的な意図があって初めて成立する。しかし、「生存」や「進化」といったものは、進化論的には単なる結果であり、意図された目的とは言えない可能性がある。
第三に、価値の前提が必要である。
目的が成立するためには、それが価値あるものと認識されなければならない。例えば、「知識の拡張が目的である」と考えるためには、「知識が価値あるものだ」という前提が必要となる。もし価値が普遍的であるならば、目的も固定されるが、価値が文化や時代によって変わるならば、目的も変化する可能性がある。
4. 目的の存在についての議論
目的は本当に存在するのかについては、主に2つの立場がある。
一つは、目的実在論の立場である。
この立場では、目的は確かに存在し、それは主観的に設定されるもの(個人や集団が決める目的)や、客観的に存在するもの(進化論や宇宙の法則から見出される目的)として説明できる。例えば、「人間は幸福を求めるべきだ」「生命の目的は生存と繁殖だ」といった考えがこれに当たる。
もう一つは、目的否定論の立場である。
この立場では、目的は後付けの概念にすぎず、進化や物理法則の結果を「目的」として解釈しているだけにすぎないとする。例えば、「生存や進化は単なる結果であり、目的ではない」「宇宙に目的はなく、すべての出来事は偶然の産物である」といった考えがこれに該当する。
もし目的が存在するなら、それは意識的に設定されるものか、システムや環境に内在するもののいずれかとなる。一方で、もし目的が存在しないならば、「目的とは単なる人間の解釈にすぎない」という結論に至る。
5. 結論
目的という概念は単純なものではなく、主観・客観・システム・環境など、さまざまな要因によって規定される多層的な構造を持つ。
目的を持つためには、主体・意図・価値の3つの条件が必要と考えられるが、目的は固定的なものか可変的なものか、また本当に存在するのかについては議論の余地がある。
この前提をもとに、次に「人類の目的とは何か?」を探ることが、論理的な流れとなる。

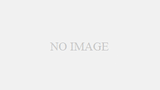
コメント